
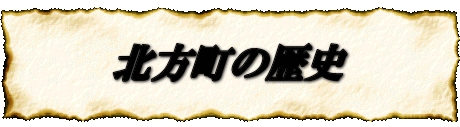
円鏡寺は、いつ頃建てられたか。
いつのころからか、糸貫川の東岸にお堂があり、
東山道を旅する者が旅の安全を祈願していました。
糸貫川は根尾川の本流で水量も多く、大雨の時などには渡ることができず、
旅人はこの寺を宿泊所、休憩所として利用したと考えられる。
ところが、火災かあるいは洪水によって寺は倒壊してしまい、
それを平安時代(今から1000年ほど前)に良祐上人(りょうゆうしょうにん)というお坊さんが中心になって建て替えたのが今の円鏡寺です。
こうして円鏡寺はこの地の中心として大切にされ、武士の時代になると土岐氏に守られ、多くの仏像などが作られ、今も大切にされています。
円鏡寺には、どんなお宝があるか。
円鏡寺には、織田・豊臣・徳川も篤く信仰を寄せ、その繁栄ぶりは今に残る数々の文化財からしのばれ、
国の重要文化財に指定された楼門と仏像など、たくさんの名品の数から、「美濃の正倉院」とも呼ばれています。
円鏡寺の中で指定されている、重要文化財、天然記念物

