
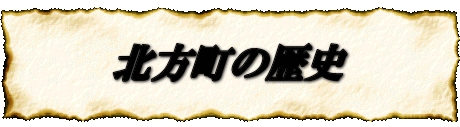
※写真 11月4日撮影 |
![]() 時の太鼓とは何か。
時の太鼓とは何か。
江戸時代に北方の土地は、加納藩の支配を受けていましたが、藩主の弟の戸田光賢(光直)が初代の領主となり、この土地を治めていました。
1697年、光賢が時の将軍、徳川綱吉に披露した馬術が大変素晴らしいとほめられ、
そのほうびに「冠木門(町立図書館の入り口に復元されている)」や「時の太鼓と打法」を許されました。
その打ち方は徳川御三家(水戸、尾張、紀州)にしか許されなかった貴重なものです。
明治の始めに本町より現在の場所に移転されました。
![]() 戸田光賢が将軍の前で馬術を披露した時の様子
戸田光賢が将軍の前で馬術を披露した時の様子
光賢は武芸に大変すぐれていて、特に馬術には優れた才能を持っていました。
そのため将軍綱吉は、是非とも光賢の馬術を見たいと思い、光賢を呼び寄せました。
1697年4月12日、江戸城の桜田門の前に長さ約164m、幅5.5mの馬場を築き、光賢は将軍の前で演技を披露したのです。
その演技があまりにも素晴らしく感動した将軍は、翌日も演技をするように光賢に伝え、早朝からさらに難しい数々の演技を披露しました。
さらにその翌日には、品川沖で水上馬術を披露しました。
3日間にわたる将軍の前での馬術の披露を見事にこなした光賢は、将軍から何か希望するものをほうびとして差し上げようと言われ、何度も断ったが、
将軍の気持ちをくみとり、時の太鼓を打つことを願い出て、許可された。
そして1698年4月13日、時の太鼓が初めて打ち鳴らされたと言われています。
![]() 太鼓顕彰の様子
太鼓顕彰の様子
裃に正装し、昔ながらの出で立ちで、文化財保護協会の方々が時の太鼓を打ちます。
昔から伝わる太鼓の打ち方が再現され、
はじめは小さく早くおわりは高く打ち上げられた太鼓の音は、何ともいえず、北方の町に響きます。
また、地元の子ども会の子どもちは太鼓櫓に登り、一人一人時の太鼓を打ちます。
一般の方も太鼓を打つことができるので、是非北方町に来て、時の太鼓を打ちに来てみてはいかがですか?
 ←裃を着て時の太鼓を打つ、文化財保護協会の方々
←裃を着て時の太鼓を打つ、文化財保護協会の方々
※画像提供 町の概要 岐阜県北方町