
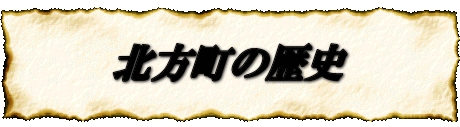
 |
|
![]() 美濃派俳諧水上道場跡とは。
美濃派俳諧水上道場跡とは。
江戸時代の中期から、北方の経済は活発となり、この経済力を土台にして文芸活動が盛んとなりました。
その1つが「俳諧」です。
現在、西運寺の境内に「美濃派獅子門水上道場」の跡が伝えられています。
![]() 美濃派獅子門道場とは。
美濃派獅子門道場とは。
美濃派獅子門は松尾芭蕉の流れを引いた俳諧の流派です。
単価の上の句《五七五》と下の句《七七》は別の人がつくり、お互いに競争するように句をつくっていくのです。
北方出身の人が宗匠になったので、獅子門の中心が北方に移ったようでした。
宗匠になると全国をまわって門人を指導するので、経済的にも恵まれていなければなりませんでした。
それができたのは北方には全国に向けて商売をするような商人がいて、経済的にゆとりがあったからでしょう。
![]() どんな人々がおられたのか。
どんな人々がおられたのか。
北方で俳諧が盛んになったのは、美濃派を開いた各務支考(松尾芭蕉の弟子の中でも特別優れた弟子)の後継者である仙石盧元坊が北方の出身であって、
全国に美濃派を広めたことや、この町に多くの弟子を育成したからです。
盧元坊の作風は、分かりやすい言葉で人生をたくみにうたっており、明るい表現であったと言われています。
その後を五竹坊、再和坊・・・と北方ゆかりの人が受け継ぎ「北方派」とも言われるぐらいに盛んでした。
水上道場は五竹坊が師弟を指導した場所で、歴代の宗匠をしのぶ石碑が並んでいます。
![]() 美濃派水上道場跡には、どんな俳諧が石碑として残っているのか。
美濃派水上道場跡には、どんな俳諧が石碑として残っているのか。
美濃派水上道場跡には25の俳諧が石碑として残っています。
下の写真のように石碑が並べてあります。


それでは、入口向かって左からどんな俳諧があるのかを紹介していきます。
※○○翁
年をとった男
※○○庵
よく俳諧の石碑にその俳諧を読んだ人の名前が、○○庵で終わっているが、
文人、学者、画家、茶人などが、本名以外につける風雅な別名として付けられている。