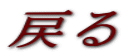●岐阜提灯の起源→推定17世紀ごろ
岐阜で提灯が製造され、尾張藩を通して幕府に献上したとされています。現在のような柄や形ではなく、一般的な提灯であったそうです。
現在と変わらずこの頃も提灯に美濃紙が広く用いられました。その後少しずつ基本形が出来、発展を遂げて現在の形に至っています

●岐阜提灯の起源→推定17世紀ごろ
岐阜で提灯が製造され、尾張藩を通して幕府に献上したとされています。現在のような柄や形ではなく、一般的な提灯であったそうです。
現在と変わらずこの頃も提灯に美濃紙が広く用いられました。その後少しずつ基本形が出来、発展を遂げて現在の形に至っています
宝暦年間(1751〜63年)に現在の形の岐阜提灯が登場しました。この頃はまだ白無地でしたが、
文政年間(1818〜29年)に彩色を施した提灯が登場しました。
この時代の貴族たちの俳句にも多く残っているそうです。
| ●特徴 | |||
| ・細骨に美濃和紙などの薄紙を張り、通常は長卵形の吊(つるし)提灯 | |||
| ・薄紙には美しい模様が施されている | |||
| ・手作業が多く、技術として「張り」(細骨に薄紙を張る)、「擦り込み」(薄紙に模様を版画の要領で摺る)、「盛り上げ」がある |
盛り上げというのは提灯の木の部分に白胡粉(しろごふん:日本画や日本人形の絵付けなどに使われる顔料)で盛り上った模様を施す、
といったことですが、簡単に言うと提灯の一番下の木の部分などに絵を描く際に、絵具を使って立体的な模様を描くということです。
盆灯籠(ぼんとうろう)にも使うため盆提灯とも言います。
----------------------------------------------------分業制について--------------------------------------------------
「分業制」というのは、ひとつのものをつくるのに、パーツごとなどで作業を分割して行う制度です。
それぞれ熟練したプロの職人さんが行っています。岐阜提灯もこの制度を取り入れて作業を効率化しています。
はじめの頃は問屋が向上をもち、職人を雇って作るという流れでしたが、需要が増えるにつれて各製造工程の分業化が進み、口輪(くちわ)屋、塗師、
蒔絵(まきえ)師、板目彫(いためぼり)師、摺込(すりこみ)師、張屋(はりや)に独立しました。それぞれ問屋の発注を受けて生産が行われています。
絵柄について↓
絵柄をつけるための大事な工程に、「刷り込み」、「絵付け」があります。
岐阜提灯はこのどちらかの方法で作られています。
「摺り込み」・・・型紙を用いて、まだ骨に張り合わせる前の紙に絵を刷り込む方法です。この作業をする職人さんを「蒔絵師」といいます。
「絵付け」・・・無地の紙を提灯骨組に貼って提灯を作り、その後で絵を手がきで描くという方法です。