くうちゃんの写真もあります↓
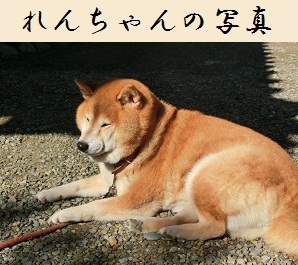
*本院*
まずは本坊(南庭)から紹介します。

南庭の池の造りは、平安時代の寝殿造りの様式により、
洲浜、遺水、船付場が設けられています。
浄土庭園では、池の形は普通梵字の「ア」字とされていますが、
ここは金剛界の文字「バン」としています。
「カキツバタ」の池は南庭の梵字の「バン」の上に付ける点とします。
そして池にはたくさんの鯉が泳いでいます。
下の岩は白蓮女史歌碑といい、
柳原白蓮女史が昭和27年に延算寺にお参りに来て
小野小町のことを詠んだものです。
つぎに本院とその周りの建物の紹介です。

本院は、桁行三間、梁間四間、単層入母屋造の本堂です。
外観は優美で均整のとれた素朴な建物。
組物・蟇股(かえるまた)などの彫刻に室町時代の様式を残しているが
現本堂は、兵火で消失したものを、寛永二十年(1643)淳仁法印(じゅんにほういん)が再建したものである。
本来は桧皮葺屋根であるが、
昭和三十六年解体修理の際銅版葺としている。
↓↓
除夜の鐘は年の初めに鳴らしに行きます。
年越し蕎麦なども配っていて
大勢の人でにぎわいます。
この時期は紅葉と一緒に両方楽しめるし
上からの眺めは最高です!
この写真は「ヤマモモ」といい
市天然記念物にも認定されています。
ヤマモモはヤマモモ科の常緑広葉の高木で、
雌雄異株です。樹皮や根皮は薬用に用いられることがあり、
雌株は甘酸っぱい独特の風味をもち
果実を初夏に多数つけ、食用にされることもある。
ヤマモモの名称は、その紅い実が生で食べられることから
ついたものですが、果物のモモとは全く違った種の植物です。
まんだら山の入口です。
まんだらというのはたくさんの仏様の集まっている仏の浄土(美しい世界)という意味があるそうです。
毘沙門堂
昭和6年に東院本堂(かさ神)を移築したものだそうです。
大師堂
堂内には、弘法大師、不動明王、愛染明王
金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)、胎蔵界曼荼羅、などがあります。
↓リンク↓