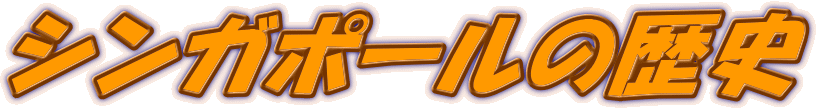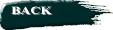
| 〜〜〜〜〜〜シンガポールの歴史と産業の発展〜〜〜〜〜〜 中国の元代末に2度にわたって東南アジアを広く旅した汪大淵の旅行記「島夷誌略」の中に、「トゥマセク(シンガポールの古名、海の町の意)が、外国船も立ち寄る港町であること、やせ地で稲作ができないため、住民は海賊を生業としていること、住民のなかには中国人もおり、彼らは土着民と同じ服装だったこと」などが記されている。 トゥマセクがシンガプーラ(獅子の町)と名前が変わった事情については、いろいろな説がある。マジャパイト支配下の都市は、通常シンガプーラと呼ばれていたとか、「シンガ」は単に「寄港」を意味し、シンガプーラは「寄港地」の意にすぎないとか。 シンガポールの中学校教科書は、スマトラから来た領主サン・ニラ・ウタマが町を建設し、名をシンガプーラに改めたという説をとっている。 <近代都市の形成> 1819年1月に、ラッフルズが上陸した地点を示しているのが、シンガポール川のほとりの白いラッフルズ像があるところだ。 この上陸が近代シンガポールの幕開けとなった。イギリス東インド会社の書記であったラッフルズは、中継港建設の場所を探して、ここに上陸したのである。彼は、この島をその場所と決め、シンガプーラを英語風のシンガポールに改め、都市計画の図面を引き、無関税の自由港政策を定めて、シンガポール反映の基礎を築いた。ラッフルズこそ、近代シンガポールの父なのである。 自由港の魅力に引かれ、東南アジア各地、中国、インドなどから多くの商人が移り住み、シンガポールはまたたく間に東南アジア随一の貿易都市に成長した。19世紀後半から、マラヤ(マレー半島)ですず鉱山とゴム農園の開発ブームが起こり、その労働者として中国・インドから多くの移民が入ってきた。シンガポールはマラヤ産品の集散地、マラヤを含む移民コミュニティの中心地となってますます発展した。 シンガポールへの移民も、19世紀後半から急増し、20世紀前半には、シンガポールの人口は20万人を超え民族別では、華人:75%、インド人(南アジア):6〜7%、マレー人(東南アジア)15%程度という、現在とだいたい同じ比率になった。 移民達は、移民別にコミュニティを形成し、それぞれの言語・宗教・文化を守って生活したので、シンガポールは多様な人々が融合せずに、サラダボウル状に存在する「複合社会」となった。 <安定と繁栄> 経済においても、国際環境がシンガポールに味方した。1960年代の世界的な投資ブームと貿易の拡大は、シンガポールの主要産業である貿易・金融を急成長させ、外資誘致も順調に進んだ。特に、日本企業の海外進出と時期が重なったため、シンガポール政府は、日本企業の誘致に力を入れ、めざましい成果を上げた。独立後30年間、年平均10%成長という驚異的な経済発展を続け、1990年代には堂々たる先進国となった。失業は1972年ごろに解消し、その後は労働力不足となって、外国人労働者が増えている。 現在では、観光業が中心となっており、そのためテーマパークや施設などが多くなっている。 |